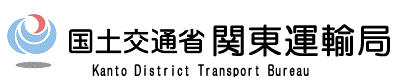
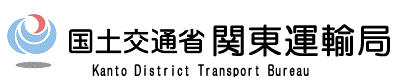 |
|
|
|
|
|
| 関東管内の地域鉄道にある珍しい駅名等をいくつか紹介します。鉄道を利用する際に、珍しい駅や特殊な駅を探してみることで、新しい魅力を発見することができるのではないでしょうか。 | |||
|
|||
| ①関東鉄道株式会社(常総線) | |||
・大宝駅(たいほうえき) |
|
||
|
|||
| ・騰波ノ江駅(とばのええき) 駅名の由来は、万葉集に「鳥羽の淡海(おうみ)」と歌われている大きな湖沼が存在したことから、「騰波ノ江駅」と名付けられました。また、旧駅舎は「関東の駅100選」に認定されています。 |
| ||
| ②野岩鉄道株式会社 | |||
| ・男鹿高原駅(おじかこうげんえき) 昭和61年10月に開業した無人駅です。高原の中に静かにたたずむ栃木県で最北端の鉄道駅になります。雑誌等でも「何もない駅」として紹介されるほど周囲に何もなく、聞こえてくるのは、谷川のせせらぎ、鳥のさえずり、風に揺らぐ木々の葉音のみです。ただし、毎年10月に同駅駅前広場で開催されるイベント「ビーフピアINふじわら」では多くの人で賑わいます。隣駅は福島県南会津町(会津高原尾瀬口駅)です。 ※ 駅には訪れる人が思ったことを記入するノートが あります。これ読むのも楽しいと思います。 |
| ||
| |||
| |||
③上毛電気鉄道株式会社 |
|||
| ・富士山下駅(ふじやましたえき) 山梨県と静岡県に跨がる富士山(ふじさん)の山麓にある駅と勘違いして訪れてしまう外国人観光客が年間数人見受けられます。 名前の由来は、群馬県桐生市の富士山(ふじやま)の山麓にある駅ということであり開業当初(1928年)から変わらない駅名です。なお、富士山について、イコモス(世界遺産一覧表への記載の可否を決定するユネスコの諮問機関)が世界遺産一覧表への記載を勧告したことを受け、報道各社において「富士山下駅」に外国人観光客が間違えて来てしまう駅として紹介されています。 |
| ||
| |||
| |||
④上信電鉄株式会社 |
|||
| ・南蛇井駅(なんじゃいえき) 明治30年(1897)7月7日に開業した駅です。今年は蛇年であり、私鉄の駅で「蛇」が付く駅が他にないことから記念乗車券が販売されています。 南蛇井という地名の由来は、川の幅が広いところというアイヌ語「ナサイ」が語源という説と周辺の井戸から大蛇が現れたことにちなんでいるという説があります。「ナサイ」と呼ばれていた地名は、古墳時代~中央集権国家成立の頃には「那射(ナザ)郷」となり、更に転じて「なんじゃい」になり、そこに「南蛇井」という漢字をあてたとも言われています。奈良時代には、すでに南蛇井氏という豪族が存在していたようです。 |
| ||
| |||
| |||
| |||
⑤わたらせ渓谷鐵道株式会社 |
|||
| ・神戸駅(ごうどえき) 「神戸(こうべ)駅」と読むことができるため、開業当初は、兵庫県神戸市にある東海道本線・山陽本線 神戸駅との混同を防ぐため、本来の地名とは別の漢字を用いて「神土(ごうど)駅」と名付けられました。その後、わたらせ渓谷鐵道への転換時に本来の地名にあわせ「神戸(ごうど)駅」に改称されました。 |
| ||
| ・沢入駅(そうりえき) 駅舎内に簡易郵便局を併設した駅です。無人駅扱いのため、郵便局で乗車券を購入する事はできません。下りホーム側には、東屋や遊歩道などが整備されています。 |
| ||
| |||
⑥銚子電気鉄道株式会社 |
|||
| ・本銚子駅(もとちょうしえき) 「ほんちょうし」と読むことができる為、験担ぎの駅としても有名です。また、近年は「上り銚子開運切符」が人気となっています。 |
| ||
これらの駅名に限らず、聞き慣れない珍しい駅名に着目することは、列車に乗る時の楽しみとなり、旅の思い出の一つになると思います。これからの暑い夏は地域鉄道で自然を感じるとともに特別な駅を探す旅に出かけてみては如何でしょうか。 |
|||
| |||
|
Copyright© Kanto District Transport Bureau All rights reserved
|