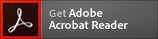2025�N10��31�� �X�V
�k�C���^�A�ǍL�w�k�l�����x��Q�W�P���i�ߘa�V�N�P�O���R�P�����s�j 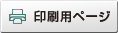
�ڎ�
- �ߘa�V�N�x �S���W���J�ғ��\���������s���܂���
- �����Ԏ��̖h�~�Z�~�i�[���J��
�`�g���b�N�E�^�N�V�[�E�o�X����X�O�����Q���` - �^�]��s��������
�`�ސE�\�莩�q�������A�E������E�^�]�̌��������Ǔ��ŏ��J�Á` - ��������ψ���ƍ���������蒲�������{
�`�g���b�N�E����G�����@�W���Ď����ԁ` - �C���Y�ƂŊ���t�l�[�W�����A���������w�Z�ɍ��N���㗤�I
�ߘa�V�N�x �S���W���J�ғ��\���������s���܂���
 �y�^�A�ǒ������z
�y�^�A�ǒ������z
�@�ߘa�V�N�P�O���P�S���i�Ηj���j�A�D�y��Q�������ɂX�K�u���ɂ����āA�ߘa�V�N�x �S���W���J�ғ��\���������s���܂����B
�@�S���W���J�ғ��\���́A�S���W���Ƃł����ꂽ���ɑ��A�e����(�S���E������)�̂����тɌh�ӂ�\���āA�S���̓��i�P�O���P�S���j�ɂ��킹�Ď��{���Ă���A���N�͓S���W���J�҂R���A�^�]�����̕\���V���Ǝ҂�\���������܂����B�\�����ɂ́A��҂̊F���܂ɂ��o�Ȃ��������ƂƂ��ɁA���o�y�ъW�҂̕��X�ɂ���Ȃ��������܂����B �@
�@�\�����ɂ������ẮA�k�C���^�A�ǒ��̎����A�\������^�A�����ė��o���\���ē��{�ݕ��S��������� �k�C���x�В��@�u���@�m �l���炲�j�����A��҂���͎D�y�s��ʋ� �~�@�ˎi �l����ӎ������������A��Ȃ����������܂����B
�@��܂��ꂽ�F�l�̉v�X�̂�����Ƃ������A���тɋƊE�̍X�Ȃ邲���W�����F��\���グ�܂��B

�y�\������^�z

�y��҂̊F�l�z
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/20251007_00002.html
�����Ԏ��̖h�~�Z�~�i�[���J��
�`�g���b�N�E�^�N�V�[�E�o�X����X�O�����Q���`
�@�k�C���^�A�ǂł́A��ʎ��̂ɂ�鎀�Ґ��A�d���Ґ��A�l�g���̌����̍팸��ڎw���u�k�C���^�A�Lj��S�v�����Q�O�Q�T�v�̈�Ƃ��āA���Ɨp�����Ԃ̎��̖h�~��ړI�Ƃ����u�����Ԏ��̖h�~�Z�~�i�[�v���P�O���P�U���ɊJ�Â��܂����B
�@�{�Z�~�i�[�͕����Q�W�N�x�ɏ��߂ĊJ�Â���A���N�ő�7��ڂ��}���܂����B��N�x�Ɉ��������A���N�x�������̂��\�����݂����������A�g���b�N�E�^�N�V�[�E�o�X�̊e�ƑԂ��疞�ՂȂ��A��X�O���̊F�l�ɂ��Q�����������܂����B
�����́A���O�̗L���҂ɂ��4�̊�u�������{�����ق��A�u�i�X�o�M�������[�v��u�^�C���̒E�����̖h�~�[���v�̓W���������ōs���܂����B�܂��A���t���A�̉�c���ł́A�ŐV�̃f�W�^���^�R�O���t��h���C�u���R�[�_�[�̋@��W�������{���܂����B
�@�k�C���ŊJ�Â���鎖�̖h�~�Z�~�i�[�ɂ����ċ@��W���͍����̎��݂ł������A�Q���҂̊F�l����͑�ς��D�]�����������A�e�u�[�X�ł̐����ɔM�S�Ɏ����X���Ă��������܂����B
�@�k�C���^�A�ǂł́A������W�c�̂ƘA�g���Ȃ���A�����Ԏ��̖h�~�Ɍ��������g�݂�ϋɓI�ɐ��i���Ă܂���܂��B
���J��A
�@�k�C���^�A�ǁ@�����ԋZ�p���S�����@���@�p�a

���u���P�u���Ɨp�����ԑ������S�v�����Q�O�Q�T ��g�̍ŐV�ɂ��āv
�@�u�t�F���y��ʏȁ@�����E�����ԋǁ@���S����ہ@���S���W���@�p�c�@�T�g�Y�@��

���u���Q�u�����^�]�o�ł̂��ߍ��ł��邱�Ɓv
�@�u�t�F�Ɨ��s���@�l�@�����Ԏ��̑�@�\�@�D�y��ǎx���@�A�V�X�^���g�}�l�[�W���[�@�����@�T��@��
�@�����^�]�̌������̌o�܂�@�߁A�A���R�[���̑̓��c�����ԁA�_�Ď��̒��ӓ_�Ȃǂ̂��Љ�ƈ����^�]�̔w�i�ɂ���l�̓����ɉ���������̏d�v����ߎ��Ɍ������������P�̃q���g�ȂǁA���H�I�Ȏ��̖h�~��J�ɂ�������������܂����B

���u���R�u�f�W�^���^�R�O���t��p���������Ԏ��̖h�~�ɂ��āv
�@�u�t�F��ʎВc�@�l�@���{�^�R�O���t�������ƎҍH�Ɖ�
�@��NP�V�X�e���J���@�k�C���x�X�x�X���@���@�S��@��
�@�f�W�^���^�R�O���t�́A���x�E���ԁE�}�������Ȃǂ������I�ɋL�^���A���S�^�]����јJ���Ǘ��̗��ʂŊ��p����鑕�u�ł��B�{�Z�~�i�[�ł́A�x���@�\�A�^�]�]���A�댯�^�]�A�S�����ԊǗ��Ȃǂ̋�̓I�Ȋ��p�����ʂ��āA���̖h�~�ƋƖ��������ւ̗L�����ɂ��Ă��������������܂����B

���u���S�u�h���C�u���R�[�_�[��p���������Ԏ��̖h�~�ɂ��āv
�@�u�t�F��ʎВc�@�l�@�h���C�u���R�[�_�[���c��@��@�i��@���v�@
�@�h���C�u���R�[�_�[�́A�q�����E�n�b�g�⎖�̂̉f���E�Z���T�[�f�[�^���L�^���A��ʎ��̖h�~�Ɋ��p����Ă��܂��B�{�Z�~�i�[�ł́A���W���ꂽ�f�[�^�����ƂɁA�^�]�f�f�A���S����A�����^�]�Z�p�̕]���A���̏����x���Ȃǂւ̊��p�ɂ��āA������₷�����������������܂����B

���W���P�u�i�X�o�M�������[�v
�@�Ɨ��s���@�l�@�����Ԏ��̑�@�\�@�D�y��ǎx��
�@��ʈ⎙��d�x����Q�҂̕��X���O�����Ɏ��g�ގp���\�����ꂽ�G��E�ʐ^�E�����Ȃǂ̍�i��W�����A���̔�Q�҂̎x������S�^�]�ւ̈ӎ������i���܂����B

���W���Q�u�ԗ֒E�����̖h�~�[���v
�@�k�C���^�A�ǁ@�����ԋZ�p���S��
�@�~�G�ɑ��������^�Ԃ̃^�C���E�֎��̂�h�~���邽�߁A�W�@�ւƘA�g�����[�����������{���A�i�b�g�̒��ߕt���m�F���C���_���̏d�v�����Ăт�����X���L�����y�[���̂ق��A�u���E�ƁE���E�ȁE���v�̃`�F�b�N�|�C���g�i�_�������E�g���N�Ǘ��E���я����E�������h�z�E���X�̓_���j�̎��m��ʂ��āA���̖̂��R�h�~�ƈ��S�^�s�̊m�ۂ��Ăт����܂����B

���W���R�u�f�W�^���^�R�O���t�E�h���C�u���R�[�_�[�@��W���v
�@��ʎВc�@�l�@���{�^�R�O���t�������ƎҍH�Ɖ�@����S��
�@�@���G�i�W�[�V�X�e�����A���f�[�^�E�e�b�N�A�������[�^�[�������A��NP�V�X�e���J��
�@��ʎВc�@�l�@�h���C�u���R�[�_�[���c��@����T��
�@�@�e�N�m�R���A�G�t�@�[�h���A���g�����X�g�����A�����s�e���A���R���e�b�N
�@�ŐV�̃f�W�^���^�R�O���t����уh���C�u���R�[�_�[�̋@��W�����s���A�Q���҂����ۂ̋@��ɐG��Ȃ��玖�̖h�~��Ɩ��������Ɋ��p�ł���@�\�⊈�p���@�ɂ��ė�����[�߂�@��ƂȂ�܂����B


https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/20250912_00001.html
�y�k�C���^�A��HP�z���Ɨp�����Ԃ̎��̖h�~�Z�~�i�[���J�Â��܂��`��i�I�ȃf�W�^�R�E�h�����R���W�������܂��I�`
�^�]��s��������
�`�ސE�\�莩�q�������A�E������E�^�]�̌��������Ǔ��ŏ��J�Á`
 �y28���̎��q�����Q���z
�y28���̎��q�����Q���z
�@�ߘa7�N9��27���i�y�j���j�A����^�A�x�ǂ͖k�C����쑍���U���ǂƂ̋��Âɂ��A�ފ����ԋ߂ɍT�������q����ΏۂƂ����u�o�X�E�^�N�V�[�E�g���b�N�h���C�o�[����ю����Ԑ����m�̒S����m�ۂɌ����������A�E������E�^�]�̌���v�i�ȉ��A�u������v�j���A����Ǔ��ŏ��߂ĊJ�Â��܂����B
�@�ߔN�A�^�A�ƊE�ł́A�^�]�ҕs���ɂ��H���o�X�̔p�~�E���ցA�^�N�V�[�̉ғ����ቺ�A����ɂ́u����2024�N���v�ƌĂ��g���b�N�ƊE�̗A���\�͕s���ȂǁA���܂��܂ȉۑ肪���݉��E�[�������Ă��܂��B�܂��A�����ƊE�ɂ����Ă������Ԑ����m�̐l�ޕs�����[�������Ă���A�S����̊m�ۂ��i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă��܂��B
�y


�y���F����n��g���b�N����z�@�y�E�F����n�������Ԑ����U����z


��������ψ���ƍ���������蒲�������{
�`�g���b�N�E����G�����@�W���Ď����ԁ`
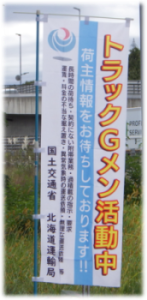
�@���y��ʏȂł́A�g���b�N�^�����Ƃɂ����������̓K��������уh���C�o�[�̘J�������̉��P�Ɍ����āA�S���Ɂu�g���b�N�E����G�����v��ݒu���A��E�������Ǝ҂ɑ��闝�𑣐i����юw���̋�����i�߂Ă��܂��B ���Ɂu�W���Ď����ԁv�ƈʒu�t���Ă���ߘa7�N10���`11���́A��������ψ���Ƃ̘A�g�̂��ƁA�厖�Ǝғ��ɑ��鍇���p�g���[����g���b�N�h���C�o�[�ւ̕�����蒲���������{���Ă��܂��B
�@�k�C���^�A�ǂł́A���̎�g�̈�Ƃ��āA�S���ɐ�삯�ėߘa7�N10��3���i���j���j�ɍ���T�[�r�X�G���A�i���E����j�ɂ����āA��������ψ���k�C���������ƍ����Ńg���b�N�h���C�o�[�ւ̕�����蒲������ю��m���������{���܂����B �����ł́A�����Ԃ̉ב҂���_��O�̕��э�ƂȂǁA��⌳�����Ǝ҂ɂ��ᔽ�����s�ׂ̗L���ɂ��ď����W���s���܂����B���킹�āA��������ψ����́A�ߘa8�N1��1�����u����^���ϑ��v�i�ꕔ�̉^���ϑ��_��j�������������K�����@�̋K���Ώۂɒlj�����邱�Ƃ�A����ɂ����鏅�玖���E�֎~�����ɂ��Ă̎��m���s���܂����B
�@�����́A���E���肠�킹��17���̃h���C�o�[����M�d�Ȃ��ӌ������������܂����B���̒��ɂ́A�u�����Ԃ̉ב҂����������Ă���v�Ƃ������ᔽ�����s�ׂ̋^���Ɋւ�����������m�F�����ȂǁA����̎����c�����邤���Ŕ��ɗL�Ӌ`�Ȓ����ƂȂ�܂����B
�@�k�C���^�A�ǂł́A���������ꂽ�������Ƃɉ哙�ւ̐����w�����s���ƂƂ��ɁA�^�A�ǂƌ�������ψ�������ʼn�p�g���[�������{����ȂǁA��������S�̂̎�����̓K�����Ɍ��������g�݂���w�������Ă܂���܂��B
�@�Ȃ��A��⌳�����Ǝ҂̍s�ד��������ŁA�g���b�N���Ǝ҂��@�߈ᔽ�ɒǂ����܂�邨����̂����������܂�����A���L�����y��ʏȉ哙�̈ᔽ�����s�ׂ̒ʕ��܂ŏ��������������B
https://gmensystem.my.site.com/FeedbackBox/s/�@
�y�哙�̈ᔽ�����s�ׂ̒ʕ��z
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000343.html
�y���y��ʏ�HP�z�u�g���b�N�E�����f�����v�̑̐����������A�W���Ď����Ԃ����{���܂�
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/20251001_00003.html
�y�k�C���^�A��HP�z�k�C���^�A�Njy�ь�������ψ���k�C���������ɂ�鍇����p�g���[�����̎��{�ɂ���

�C���Y�ƂŊ���t�l�[�W�����A���������w�Z�ɍ��N���㗤�I
�@�ߘa�V�N�P�O���V���i�Ηj���j�A�k�C���C���L��̋��^�ɂ��A�����s�����������w�Z�̂P�N���W�P����ΏۂɁu�C�̂��d���Љ�`�t�l�[�W���ɂ��C���u���`�v���J�Â��܂����B
�@�{�u���́A�C���Y�ƂɐG���@����Ȃ����w���ɑ��A�C������Ŋ��鏗�������i���t�l�[�W���j�̐��ړ͂��邱�ƂŁA���Y�Y�Ƃւ̗�����[�߁A�����̐i�H�I�����̈�Ƃ��ĊC��������ӎ����Ă��炤���Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B
�@�u�t�ɂ́A�k�C�����̊C���Y�ƂŊ���X�y�V�����X�g�Ƃ��āA�A�^�J���D���i���j���w�q�q�l�A�����C���ʉ^�i���j���c�����l�A�����m�t�F���[�T�[�r�X�i���j����ъ�l�A���قǂ��i���j�V�c����l�A�X�^�[�}�����i���j�ɓ������l�����}�����܂����B�e�u�t�����g�̋Ɩ����e����₷������������A���k������5�ǂɕ�����āA�Ɩ��Ɋւ��鎿���^��_�ɂ��ăf�B�X�J�b�V�������s���܂����B

�@���k�����̒T���S�͔��ɍ����A���O�ɍu�t�̏�����Ƃ̃z�[���y�[�W�ȂǂׁA�����^��_���������ču���ɗՂ�ł���܂����B�t�l�[�W���ɂ��v���[���e�[�V�����ɐ^���Ɏ����X���A���������p�����������܂����B �e�ǂł̃f�B�X�J�b�V�����ł͐��k����ASDGs�ւ̎��g�݂Ɋւ��鎿���A�D��ǂ̌�����ȂǁA����Љ�̊S�f�������̂���f�p�ȋ^��܂ŁA���L�����₪���A�u�t����̉ɋ����̐����グ���ʂ����������܂����B�u����ʂ��āA���k�����͊C���Y�Ƃɂ����鏗���̊��z���ȏ�ɑ������Ƃ�A�����ł��D���ɂȂ�邱�Ƃ�m��A�V�N�ȋ����������Ă����l�q�ł����B
 �@
�@
�@������A�C���Y�ƂŊ��鏗�������̎p��ʂ��āA�Ⴂ�����“�C�̎d��”�̖��͂�`����ƂƂ��ɁA�u�C�œ��������v��z�����邫�������Â���𑱂��Ă܂���܂��B

���t�l�[�W���F�D���③�D�E���p�H�ƂȂNJC������œ��������L���ے����鑢��B�C�^���A��́u�A�_�[�W���v�i�u���낮�v�A�u�������Ɓv���̈Ӂj�̌ꊴ�����߁A��Ȃ��m��D�����D��ɂ������ƍq�s����p��z�������A�E�����������C���[�W�B
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/press/20251003_00001.html
�y�k�C���^�A��HP�z�C�Ŋ��鏗���Ǝ����s�̒��w�����o��܂��@�u�C�̂��d���Љ� �`�t�l�[�W���ɂ��C���u���`�v���J��