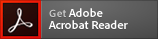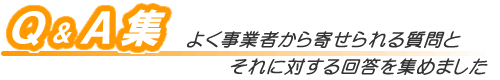
Q.倉庫で保管し、対価を得ない場合は倉庫業に当たらないか?
倉庫業とは、契約に基づいて会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
これは、物品を預かった状態で保管しておくことに対して対価を得る営業のことです。
この定義に合致しない条件の場合、倉庫業には該当しません。
他にも倉庫業にあたらない例を以下に列挙しておきます。
- 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
- 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
- ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
- 銀行の貸金庫等の保護預かり
- 特定の物品を製造・加工した後で他人に譲渡する営業、譲渡後も引き続きその物品を保管する場合も含む
- クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随してその物品を保管する行為
実際にこれらのケースと照らし合わせて、倉庫業と区別して良いのか迷うケースがあったらご相談ください。
Q.申請書に記載する際の倉庫の面積は何処まで含めるのか?
保管面積に該当する部分は、保管場所と貨物用エレベーターなど荷役の用に供する場所が該当します。
事務室と休憩室、人用の階段など保管業務や荷役業務に直接関係しない施設は有効面積には含みません。
なお、面積は小数第一位を四捨五入した整数で記載してください。
Q.トランクルームとはどのような倉庫か?また、普通の倉庫との違いは?
倉庫業法でいうトランクルームとは、寄託を受けた消費者の物品の保管をする倉庫のことです。
従って普通倉庫との違いは、預かる物が消費者からの寄託貨物のみを取り扱う点のみですので、トランクルームの施設設備基準は普通倉庫と同じです。
Q.坪貸し(倉庫の部分貸し)は可能か?
施設内の営業倉庫用部分以外の坪貸し自体は可能ですが、営業倉庫内に他者が容易に出入り出来ないような遮断措置を講ずる必要があり、その境界も壁などで遮断し人及び貨物用エレベーターもそれぞれの会社が別々に使用出来るなどの措置が必要となります。
この場合、間仕切壁は倉庫施設設備基準で定められている外壁の強度を確保するか、荷崩れ防止措置を講ずる必要があります。
Q.倉庫にマテハンを設置したが、変更の登録の申請が必要か?
この場合、特に保管室や荷役場の機能を損なうこととは認められませんので、特段減坪申請のような手続きは必要ありません。
流通加工用のキャスター付き作業台についても同様です。
Q.外壁に窓があるが、施設基準上なにか問題があるか?
窓自体が縦と横それぞれ1mを超えなければ特に問題ありません。窓が1mを超えた大きさの場合、たとえ外壁自体が基準強度を満たしていても角材や鉄格子をつけたりするなどの補強措置が必要になります。
また,JIS規格のS-6以上の強度を有している場合は例外的に補強措置がなされていると見なされます。その際は、その窓がS-6以上の強度を有している資料等が必要になります。
Q.外壁強度が2,500N/平方メートルを超えていることの証明はどのようにすれば良いか?
施設基準によると、倉庫の軸組みや外壁構造などによって基準をクリアする施設が列挙されています。これにあたる施設は図面や関係書類を添付して証明して下さい。該当しない場合は建築士事務所の証明書が必要になります。
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造の場合
- 特に添付の書類必要なし
S造の場合
- 鉄骨造の場合は荷摺り・内壁部材・胴縁が条件に合っているかが問われます
荷摺りを取り付けているときは、荷摺りが76cm以下の間隔で取り付けられていてなおかつ胴縁が90cm以下の間隔であるか。
また、下地板や内壁があるときは材質により基準に沿った厚みがありかつ90cm以下の間隔の胴縁になっているか。(詳しくは倉庫一般の施設設備基準をどうぞ)
外壁に ALC 板・ PC 板を取り付けている場合
- ALC板やPC板を使っているときは、それを製造したメーカー等の強度に関する資料が必要になります。
Q.外壁強度が2,500N/平方メートルない場合、申請可能か?
外壁強度が基準の強度を満たしていないといっても、それ自体で倉庫業の登録申請が出来ないわけではありません。荷崩れが起きないように、また起きても外壁に影響ないような措置をとっていれば可能です。
1. ラック保管をする場合
- ラックの配置状況のレイアウトを平面図に記入して添付して下さい。
2. 外壁から離して保管する場合
- 荷を外壁から離すと共に、積み上げた高さ以上の距離に保管してください。
平面図にどれだけ離したか図示すると共に、実際の倉庫にもその個所に白線を引きその範囲内に荷を置くようにして下さい。
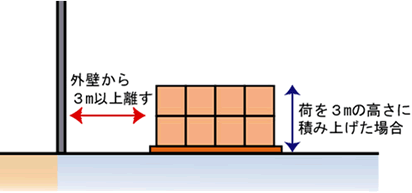
上記の場合は、外壁から3m以上離して貨物保管すること
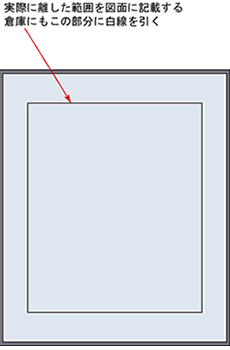
Q.事務所は防火区画で区画しなければいけないのか?
倉庫内の:事務所、更衣室、休憩室、宿直室、詰所、ボイラー室などは施設基準上火気を使用する施設と見なされ防火用の区画が必要になります。
禁煙にする、ストーブを置かない、などというように火気を一切使用しないようにしても同様です。
その区画とは倉庫が耐火建築物・準耐火建築物であれば、準耐火構造材質の床か壁または特定防火設備で区画されていることが求められます。
それ以外の構造の倉庫であれば防火壁等で区画されていることが基準を満たす条件となります。
なお、特定防火設備とは旧甲種防火戸のことを指します。
防火区画がなされているかどうか図面で確認できるようにしてください
Q.継続使用の軽微変更届出書を提出できる場合はどのようなケースか?
現在営業倉庫に使われている倉庫を他の倉庫業者が営業倉庫として使用する場合、事後の届出で済む制度があります。軽微変更届出書の継続使用がこれにあたりますが、現状のまま引き続き使用することが条件となっていて申請扱いになってしまうケースがよく見られます。
以下に軽微変更届できるケースと申請のケースを例示します。
なお、倉庫を引き渡した事業者は後でその倉庫の廃止の届出が必要になりますのでご注意ください。
軽微変更届で出来るケース(前提条件)
- 倉庫業者から倉庫業者へ営業倉庫として引き継ぐこと
- 登録時から倉庫の主要構造に変更がないこと
- 登録を受けた面積を全て引き継ぐこと
- 一棟の倉庫を一つの倉庫事業者が全て使用している場合A倉庫事業者がB倉庫事業者に引き継ぐ
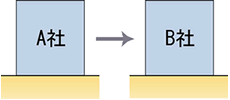
- 一棟の倉庫を複数の事業者が使用している場合A倉庫業者使用部分をC倉庫業者に引き継ぐ
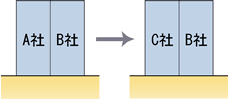
- 一棟の倉庫を複数の事業者が使用している場合(フロアごと)A倉庫業者使用部分をD倉庫業者に引き継ぐ
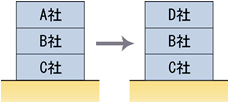
- 1つのフロアを複数の事業者が使用している場合A倉庫業者使用部分をC倉庫業者に引き継ぐ
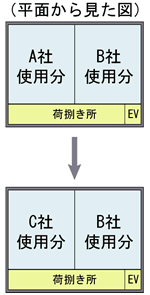
軽微変更届出来ない場合(変更登録申請が必要)
- 倉庫業者Aが使用していた部分の一部を倉庫業者Bが使用する
この場合、A社は変更登録申請(減坪)がB社も変更登録申請(新設)がそれぞれ必要になります
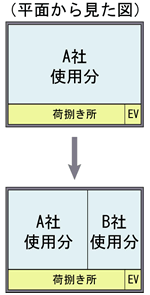
Q.倉庫内に定温庫を設置する予定であるが手続きは必要か?
現在登録を受けている倉庫内に定温庫を設置する際は、軽微変更届が必要となります。
軽微変更届出書に定温庫の配置場所を示した平面図、定温庫の面積を内数として記載した倉庫明細書を添付してください。
ただし、設定温度が10度以下の場合は冷蔵倉庫となりますので、類別の変更登録申請が必要となります。
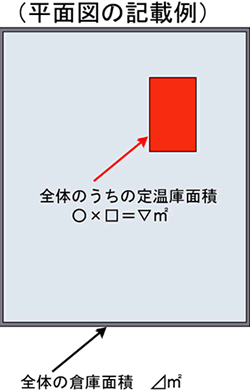
Q.倉庫内に中2階の床等を設置する際には手続きは必要なのか?
倉庫内に中2階の床等を設置する(貨物の保管に供し、作業員が搬出入等の作業を行うことができるよう増床する)場合、規模の拡大を伴う主要構造の変更ということで変更登録申請が必要になり、積載荷重3,900N/㎡以上の強度が必要です。
Q.倉庫明細書の記載について、注意すべき事項はありますか?
よくある間違いには以下のようなものがあります。
・倉庫の名称:会社名や営業所名は不要です。倉庫名のみ記載してください。
例 :(正)横浜倉庫 (誤)□□□株式会社 横浜倉庫
例2:(正)第一倉庫 (誤)東京営業所 第一倉庫
・所在地:所有庫は建物登記簿記載の所在、借庫は賃貸借契約書に記載の住所を記載してください。
・主要構造:骨組みだけではなく外壁・屋根の構造及び階数も記載してください。
例:鉄骨造 カラー鉄板張り カラー鉄板折版葺 2階建
・面積の算出法:まず各階ごとに面積の小数点第一位を四捨五入し整数にしてください。次に四捨五入後の各階の値を合計したものが保管面積となります。